On Reliability in Life History from the Viewpoint of Process in Making and Presenting a Narrative Life History "Koujutsu no Seikatsushi"
日本の社会学におけるライフヒストリー研究史において、中野卓が1977年に発表した『口述の生活史』は、方法論的問題意識に基づくモノグラフとして、その後の展開を産む重要な出発点を形成した。中野は、この本の出版について「個人の社会学的研究提唱の、いわば私の宣言ともいうべきもの」2)であるとし、実際にこの「宣言」以降、個人の語りをライフヒストリーに構成し発表するという仕事を精力的に行い、同時にまた、その素材をオーラル・ライフヒストリーだけに限定せず、個人の日記や手記などのパーソナル・ドキュメンツを用いて、近現代の日本社会を正確に捉える目的で、個人の視点を通して、生き生きとした人生の記録を公開する作業を継続している。
京都の商家同族団からはじまり、産業組織や漁業組織の展開を地域の社会変動との関連で捉え報告してきた中野のこの「宣言」は、一部には方法論の転換という受け止め方をされながら3)、「口述の生活史」というタームを定着させ、社会学および人類学の分野において、ライフヒストリー研究もしくは個人生活史研究という研究方法の明示化に大きく貢献した。
水野節夫はこの『口述の生活史』について「研究対象上の革新」と「方法上の革新」をめざした著作であると指摘した上で、前者の意義をより評価した4)。こうした「革新」を意図した中野の試みが公刊され読者に浸透していく中で、作品それ自体は中野の当初の意図とは別の読まれ方をされるようになっていると思われる。
すなわち、『口述の生活史』が日本のライフヒストリー研究に先鞭をつけた結果、この分野におけるモデルとなり、「名人芸」「達人」といった表現にみられるように、一つの完成した到達地点を示す「バイブル」としての存在を獲得するようになってきたということだ。
その主要な理由として、聞き手としての中野の極めて抑制された介在にもかかわらず、(また、それゆえに)話者が深みのある人生の語りを行っており、人間の豊かな内的世界を開示している作品であると捉えられていると考えられる。そうであるとすれば、こうした読まれ方は、作品化のプロセスに対する読み手の側が暗黙のうちに形成した共通の前提に起因しているといえる。
本稿では、この前提を主題化し、『口述の生活史』の作品化プロセスにおける、聞き手の語りへの介在と作品化との関連という問題関心から、聞き取り調査における方法論的問題と、データの編集の際に浮上する問題とを『口述の生活史』に即して検討してみたい。
2. 聞き手の解釈は作品にどう介在していくか−『口述の生活史』の場合−
作品化のプロセスを『口述の生活史』に関して考察する作業は、別の所で以前に行っているが5)、そこでの問題関心は『口述の生活史』がなぜ、ライフヒストリー研究として成功しているか、というところにあった。素朴な言い方をすれば、どのように話者との相互作用を経てインタビューし、それをどのように編集することが、より『口述の生活史』の域に到達できるか、といった視点であった。
本稿では、調査の場面および編集を経て作品化される際に、聞き手の解釈がどのように作品に介在していくかという問題についてより絞って議論していく。以下、この問題設定の意図について少し説明しておきたい。
『口述の生活史』を論文とみるかどうかについて、佐藤健二は次のように述べる。「(『口述の生活史』)を論文として評価するには抵抗があるだろう。論文とは、明示的な分析的な解釈によって再編成された作品であるが、『口述の生活史』にはそうした明示的な問題意識の表明も、分析枠組みへの言及も少ないからである。じっさい中野自身も「研究のための科学的資料」という言い方をして、その作品に論文とは異なる性格をあたえている。」6)
これは、「個人というフィールド」におけるモノグラフをどう提示するか、というプリゼンテーションの問題と、さらには「個性をもった個人」の「生き生きした」リアリティに根ざしつつ、社会学の成果としての理論をどのようにして生み出せるか、という関心にもつながっている。はたして中野自身はどの程度理論化に対し自覚的であったのか。
小林多寿子は「インタビューからライフヒストリーへ」の変換プロセスについて、自身のデータに即して考察し、ライフヒストリーとは語り手が語った人生そのままではなく、語り手が物語るその現在時点における「意義」によって解釈された人生を、聞き手が解釈して構成するという、二重の解釈によって構成されるものであると述べた7)。この指摘は、ライフヒストリー構成に対する自覚であり、当然のことながら、どちらの解釈がより妥当性をもつか、という点についての言及ではない。ライフヒストリー構成に関わるこの二重の解釈の存在は、インタビューからライフヒストリーへと2段階にわたり通時的に起こる場合も、またインタビューの場面で共時的に起こる場合もあることを気づかせてくれる。
カウンセリングなどの臨床の場面では、どのような内容が語られようとも、それを聞き手は否定せず、対象者に何を語っても大丈夫なのだという安心感を与えながら語りを引き出すことが、臨床上の目的にとって必要である。その際、対象者の語りを通した自己表出に対しては聞き手の解釈を留保することが、その目的にとって有効である。
ではライフヒストリー研究にとってはどうだろうか。わたしたちは日常生活において身の回りの出来事や他者の行為を認識する際に、なんらかの解釈枠組みを用いる。自分の生活経験や感情の経験を他者のそれと重ね合わせて共感し、また異なる思考方法や認識様式をもつ他者に対しては、違和感を感じる水準から、極端な場合、理解の対象からまったく除外するか、憎悪の対象にするといった水準までさまざまな認識の仕方をする。こうしてオーラル・ライフヒストリーの調査場面においても、さまざまな程度の共感やあるいは違和感をもちながら、研究者は他者の人生を聞くことになる。
話者の語りに対し聞き手の解釈を留保することが、調査技法として必要であっても「そんなことがあるのだろうか」と思う話が語られる場合、どうするか。
『口述の生活史』の話者の場合、そこを突破しないと生きていくことができないという状況の中で超自然的な力の助けを得て苦難を乗り越える語りが何度か登場してくる。こういう場合、中野はこれをどう聞いたのか。1995年に出された増補版に加えられた「『口述の生活史』の意味」の中で彼は次のように述べている。
「松代さんからそういう話を聞くと、そんなはずはあるまいと否定したくなる思いよりも、むしろ、それはよかった、本当によかったという気持ちのほうが強くあらわれる。」そして「いやそんなことはないでしょう」といった、聞き手がもつ科学的合理的解釈をそれとつきあわせることはしない。そしてさらに、「間主観的な人間理解は、人間の相互理解一般にとっても、社会学における人間理解にとっても有益である」と述べ、語りそのものをある基準に照らして分析するのではなく、対象者の主観的現実そのものの全体性を理解することの重要性を強調する。(1995年版: 299ページ)
この彼自身による解説がなかった初版においては、編集自体が同様の主張をしている。中野は話者内海松代さんの語りを前面に出し、彼女の語りを中野がどのように聞いたのか、どのように解釈したのかを提示することは極力避け、そうすることで、話者の語りをそのままの語り口で聞くことを読者に期待し、結果的にモノグラフに関する早急な理論化(概念化)、あるいは既存の社会学概念で彼女の人生を分析的に説明することを拒否しているようにみえる。少なくとも初版ではそうだ。
しかし、1995年版の中で「或る女の愛と呪いの日本近代」という副題が、中野自身の「解釈」であることを次のように述べる。
「『ある女の愛と呪いの日本近代』なるサブタイトルは、庶民の個人史を通して日本近代の社会史へ微視的に迫ること、近現代に亘るが焦点は近代(彼女の21歳まで)に結ばれることを示し、欧米近代とは異なる日本近代における個人の在り方を探り、不運や呪いに自助と寛容で対処した彼女の生涯に対する私の基本的解釈を示すものだった。」(1995年版:295〜296ページ)
この解説の中で、中野はA.シュッツの「多元的現実」論によって、話者の日常世界や超自然的世界を説明する。基本的には話者の人生の回想を既存の概念を用いて要約し、説明するという形をとっている。その話者の人柄と思考、危機への対処の仕方を通して、日本人の信仰、個人という概念、あるいは義理という価値意識などについて、中野の見解を述べている。
これらは明らかに、初版ではあえて禁欲されていた解説を、読者の理解を助けるために中野が書き加えたものと理解でき、読者は改めて、中野がなぜこうしたモノグラフを提示したか、その意図を知るわけである。A.シュッツの概念がなくとも、話者の主観的世界に対する中野の理解は変わらないだろうし、この「『口述の生活史』の意味」を読む限り、話者は中野がもっている日本文化や日本人に対する理解を大きく変えたのではなく、彼が理解する日本文化や日本社会の「個人」をより豊かに生き生きとその人なりに示してみせてくれた存在だったと思われる。
この意味で『口述の生活史』はその作品全体の提示によって、中野の理論的関心を示しており、話者の語りを解釈する基本的枠組みは中野には既に用意されていた。だから初版で語りをそのまま提示することは、中野にとっては自然であり、解釈を付け加える必要はなかったわけである。
3. 調査者の理論的関心と話者の選定
話者と中野の出会いについては、『口述の生活史』の「はじめに」で、短く触れられているが、なぜ話者内海松代さんが選ばれたのかは、はっきりとは書かれていない。どういう理由から中野は内海松代さんから聞き取りをすることを決めたのか。これについて、彼女の語りの大半がすんだ後の「第10章 昭和50年前後」の冒頭で中野は次のように述べている。
「昭和四六年十二月実施の呼松の現地調査中、公害下でこの田舎町の人口が老齢化を進めていることを知ったと共に、また、老人の場合、公害から脱出しようとする移転の要求に関して、青年・壮年の層とも著しく異る意識態度のあることに注意をひかれたが、とりわけ、学生調査員の一人が、ある老婆が『弘法さまが移転なさらないのに、どうして私らが呼松を離れて他所へ移れますものか』と答えたのに強い印象をうけて、なまなましく報告してくれたことが、頭に残って離れなかった。」(1977年版:220ページ、1995年版:222ページ)
これを素直に読むと、1971年の公害に対する住民の意向調査の過程で、学生調査員の報告を受けて、中野が話者と間接的に出会ったという印象を受ける。しかし、実はそうではなく、話者内海さんに着目したのは、この委託調査が終了したあと、呼松のある地域でより小規模な形で中野が継続して行った調査の過程で、1974年夏期に調査に参加した学生の一人がまったく独自の意見を展開する内海さんについて報告したことがきっかけだったことがわかった8)。中野は「老齢にもかかわらず、村の大勢に反し唯一人批判的発言をしたの注目し、彼女の自立的個性的な人柄の形成過程を知りたくて実施した」と述べている(1995年版:295ページ)。
こうして1974年夏、内海さんの存在を知り、同年冬に郵便局でそうした意見をもつおばあさんの存在を尋ねたところ、すぐに名前と住まいを教えてもらえたという。つまり、学生調査員の報告を媒介に彼女の存在を知り、話を是非聞かせてほしい人だと思うこと自体が、話者が調査者の問題関心に対応した人であることを示している。中野が、この「自立的個性的」な人を選んだのは、「日本社会では個人が確立していない」(1995年版:298ページ)という戦後日本の知識人の間で広く受け入れられた言説への具体的反証であり、より積極的には日本社会における社会的個人のありようを示すためだった。
したがって、中野にとって、平均的な日本人を選ぶことが目的ではなく、前述の関心に沿った人であって、しかもそのような個人が、その人の人生を深く語ってくれることが必要だったわけである。まとめるならば、『口述の生活史』における話者について、調査者はきわめて選択的であった9)。
下表は『口述の生活史』の中の記載事項をもとに、呼松での調査の開始から作品の完成までを簡単にまとめたものである。録音時期の記載がないものは内容から訪問時期を特定し、話者の語りと聞き手の発話を40字30行の設定ですべて起こした文書量を訪問時期横の( )内に記した。
表1 『口述の生活史』完成までの調査過程
|
インタビュー回数が増えるほど親密になり、話題も深くなるといった関係は、必ずしもこの場合当てはまらず、一回目と二回目の調査で全体の2/3以上の語りがすんでおり、聞き取りは最初から順調に進み、主要な語りは前半で終了しているといっていい。ただし、神戸で石工庄八一家を引き取り一緒に暮らす貧しい生活の中で経験した奇跡が「ほんまにせんと思うけどなァ」という前置きで語られるのが、一番最後の4回目の訪問だったことは注目しておくべき点だろう。
4. 二つの語り方を生む話者の関心と聞き手の関心
『口述の生活史』における話者の語りは誤解される傾向がある。聞き取り場面について中野は次のように述べている。「この面接の場合、私は初めの挨拶と初めの問いかけ以外、いつも、ほとんど発言の必要がありませんでした。話は問わず語りにひとりでどんどんと展開し、私はほとんど問いを重ねる必要もないほどでした。……私はもっぱら聴き手で、ときろり、自然と発してしまう共感の声があるだけと言っていいくらいでした。」(1977年版、1995年版:5ページ)
この記述によって、わたしたちは調査場面にある種のイメージを抱く。たとえば、細々しい質問をはさまなくとも、調査者が聞きたいと思う内容を語り手が表現力豊かに、どんどん語ってくれる様子など。しかし、調査者の回想はそうであっても、実際の調査場面ではどうだったのだろうか。これについて以前「問わず語り」がどの程度、調査場面全体を通して登場するかを調べたことがある。語りにおける一回の発話量をテキストの量で操作的に定義し、インタビューの場面を「問わず語り」「問いかけ語り」「中間型」の3つのタイプに分けてみると、『口述の生活史』で用いられた録音テープのうち、話者だけが語るテキストの量が400字を越える「問わず語り」の型は全体の61%になった10)。
短い相槌だけで話者の語るままを聞く場面は、17歳(あるいは18歳)でわたった満州から帰国する際の苦難を乗り越えた話や、その後、性的暴力嗜癖のある男性と結婚して朝鮮に行き、死の恐怖にさらされながら逃げ延びて再び故郷に戻った話が典型的であり、一気に語られる様子は圧巻である。
しかし、その一方で、親族の関係や満州の日常生活については、むしろ一問一答形式であり、これらは明らかに語り手にとってさほど関心のある内容ではないが、調査者がモノグラフとして提示するのには不可欠と考える項目、あるいは調査者が関心を寄せるテーマである。
『口述の生活史』の場合を例示してみたい。
表2 聞き取り調査2回目のインタビューの一部(Mは話者、Nは調査者)
|
表3「私の父方のオジィサン徳永直十郎」(「第一章 松代の生まれる前」)への作品化
私の(父方の)オジィサンは徳永直十郎という岡山(池田)藩の侍で……、名乗りは 忘れました。私の(母方の)ヒィバァサンの生まれた家で、弟でした。私のヒィバァサンはそこから私の生まれた黒瀬家へ嫁に来たのです。 |
話者のライフヒストリーにとって重要な(と調査者が判断する)人物の来歴についてインタビューの2回目冒頭に、中野からの質問に話者が答える形で語られていく。これが表2であるが、読者に提示される際に、読み手の便宜を考慮して中野は作品としては表3のように物語を作成する。表2から表3への変換は編集ではなく作文といってよい。しかしフィクションではなく、語られた事実に即して、編者が語りを構成している。
構成とは、このように純粋な語りでは作品として不十分(読者にとってはわかりにくい)と聞き手が判断した場合、語りに依拠したストーリー(もちろんフィクションではない)づくりが行われるのであり、『口述の生活史』においてさえ、作品化の段階ではこうした作業が行われている。
5. 〈編集されなかった語り〉にみる話者の関心と聞き手の関心と調査倫理
第二の聞き手として録音テープを聞くと、第一の聞き手の関心がそこにないために質問されずにすんだことでも、第二の聞き手からすると、深い関心が湧き「その時、松代さんはどう対処したのだろう」と質問をしたくなることも当然ある。
たとえば21歳をすぎて再婚した男性の先妻の子との関係がそれである。
表4 著者がそれ以上問わなかったために、展開されなかった話
(1)先妻の子との葛藤(インタビュー2回目の語りから)
|
(2)先妻の子との葛藤(インタビュー3回目の語りから)
|
作品では表4(2)の語りが生かされ、『口述の生活史』のなかでは表5のように編集されている。
表5 「息子と嫁と孫たちと娘と」(第十章 昭和五十年前後)への作品化
私ァ(呼松へ)嫁に来たとき、(夫には)二つぐらいの(一年半になる先妻の娘)があったん。その年から育てた娘の島子も、私によォしてくれますぜェ。四十六カ年も涙の切れ目ェないほど泣かされましたがな、だいじにしてくれますが。先月も、もう(自分で)使うてしまやァええのに、持ってくるん。銭を。−ありもせんのに−。 |
個人を一生という時間軸に平均的におこうと聞き取りの場面でも意図するなら、7歳から21歳までの記憶の語りよりもその後の「45〜6年間」の義理の娘との「涙の切れ目のない」ほどの葛藤もまた、語られるべきたくさんのストーリーをもつ大きなテーマとなる。しかし、中野はそれについて、二度、三度と積極的に聞き出そうとはしない11)。
これと対照的に、中野がかねてより、コンビナートとの関係で、水島における大地震の過去について強い懸念をもって関心を寄せていた大地震があったかどうか(1977年版:208〜214ページ、1995年版:211〜216ページ)についてはしつこいほど話者に質問している12)。そのように繰り返される入念な質問によって「いつでしたか。戦後じゃなかったかなァ。戦時中のことでしたかなァ。大きな地震。この道が、みんなヒビがはいったん」という貴重な「事実」が語られた。語りが発掘されたと言う方が正しいだろう。
こうした入念な質問によって語られる話がある一方で、入念であるにもかかわらずほとんど語られない話題もある。調査者の数度の質問にもかかわらず、夫助四郎との関わりはほとんど語られない13)。
録音テープから起こしたテキストには夫の兄の言葉として話者に対して語られた、夫の人柄を示す語りがある。「わしがなんでも弟に話すゥ、言ってはらちがあかんけん、あんたに話すりゃぁ、なんでもテキパキやってくりョォったけんと思うて、、、」。
話者以外の登場人物による夫の評価である。編集することもありえた。編集されれば、「優柔不断な決断力のない気弱な男性」イメージがつくられたかもしれない。 編集に関する中野の基本的スタイルは、『口述の生活史』をみる限り、話者の語りをとことん使い切る。たとえば、「おがんでくれんか」という形で、調査中に近所の人が登場すると、そこでのやりとりの観察をも編集に組み込み、話者の地域における位置、得ている信頼を浮かび上がらせるエピソードにしていく。
しかし、夫の兄による夫の評価は編集されていない。これと同じように編集されなかった語りとして、他には「死んだ子ども」にかかわる別のバージョンと、カァサンにかかわるエピソードがあり、これらはいずれも親族にかかわる。
『口述の生活史』において、この〈編集されない語り〉は極端に少ないが、ここからいくつかのことが考えられる。それを示したのが図1である。
「問わず語り」は話者の語りたいことがまずあり、次にそれが聞き手の聞きたいことと一致すると実現し、それは豊かな語りの展開を生む。しかし、それらが身近な関係者および話者自身に対するマイナスの評価を含む場合、もしくはそうした解釈が予想される場合、語りは編集に含まないことが聞き手の節度として期待されるだろう(〈編集されない語り II〉。
また、聞き手にとっては聞きたい話題であっても話者自身にとっては関心がないこと、あるいは語りたくないこともある。この場合、語りはあくまでも、インタビューの場面だけにとどめられ編集されないということが予想される(〈編集されない語り III〉)。また、話者にとっては関心のある話題でも、聞き手にとってはそれほどの関心がない話題の場合、語りに話題が登場しても聞き手はそれ以上の質問をせず、語りもまたそれにともなってそれ以上の展開をしないということが起こるだろう。これは編集されない以前に語りがわずかしか行われない可能性がある(〈編集されない語り I〉)。ただし話者によっては、『離島トカラに生きる男』の吉岡亀太氏の語る「宇宙と元素と原子核融合」のように、話者が語りたいが(少なくともインタビュー開始時の)聞き手には関心がなく、しかし話者自身にとってはその時点での関心事である場合、問わず語りとして登場し、そして編集されることもあるだろう。
図1 編集されない語りの存在の仕方
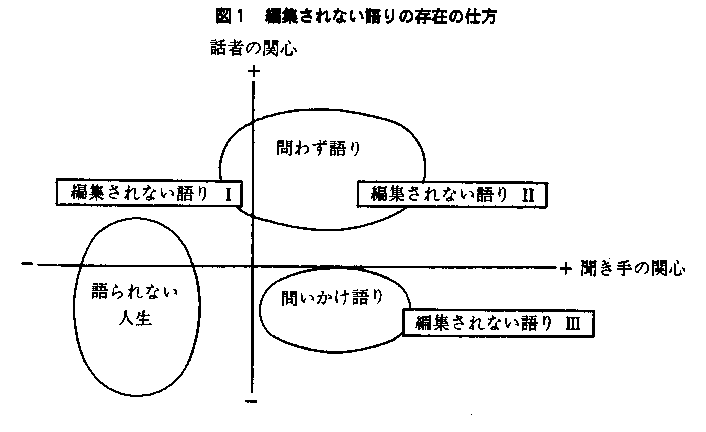
『口述の生活史』において、親族にかかわり、しかもマイナスの評価につながる可能性のある語りは編集されていなかった。もちろん、調査場面で語られることや聞き取りの中で関心をもったことを可能な限り話者に質問していくという形もあるだろう。そのようにして、知り得たことを作品として提示する段階でそぎ落としていくという方法もありえた。しかし、中野の場合、そういう方法はとらなかった。聞き取りの段階での調査者として、それ以上、聞かなくてよい(聞く必要がない)という判断の〈ふるい〉と、編集の段階での作品には提示しないと判断する〈ふるい〉とが、完全に一致しており、聞き取り段階でその一致した〈ふるい〉がインタビューに作用している。『口述の生活史』の中ではそうである。
言いかえれば、何を聞きたいのか、何を作品として提示したいのかというライフヒストリー・イメージが調査段階で明瞭であるということである。つまり、話者の構成、生き方をライフヒストリーで示すのに、義理の娘である島子との半生にわたる葛藤にかかわる語りは必ずしも必要ではないという判断の〈ふるい〉である。
もちろん、話者の親族や知人のプライバシーへの配慮が基本にあることは言うまでもない。しかし、より根本的な見方をすれば、この〈ふるい〉は中野自身の人間観に基づく社会学的関心に由来するのかもしれない。
さまざまな人生の危機にどう対処したのか。何を手がかりに、何を支えに挫折を乗り越えて生き抜いたか。そいういうライフヒストリー法への関心と通底する基本的視点が、人間の生き方の積極的な志向をより見いだしていく傾向を作り出しているのではないか。
まとめるならば、みだりに話者の身近な人々の評価(とくにマイナス評価)にかかわる領域には踏み込まないという、調査者として、編者としての自己抑制が編集されない語りを生み出している。しかし、それと同時に対象者の語りから構成するライフヒストリー・イメージもこれに関与する。ライフヒストリーを、個人の私生活の暴露話でもなく、誰かに聞いて欲しい心の悩みなどの身の上話とも区別させるのは、いま生きている諸個人が、その人の生きてきた過去をどうとらえ解釈しているのか、それを通して見える人間の社会的世界に対する深い関心なのだと思う。
こうしたライフヒストリーの構成をめざして、調査場面では、中野はどのような質問を展開しているか。次にこの質問の特徴を通して〈ライフヒストリー・イメージ〉について考えてみたい。
6. 質問が示す〈ライフヒストリー・イメージ〉の輪郭
『口述の生活史』は「問わず語り」が約6割、その他は調査者の質問と話者の回答によって構成されていると述べた。予想される以上に中野はたくさんの質問をしている。ではどんな質問か。どの程度の長さにわたるか。
これについても「長い質問」を操作的に〈40字で2行以上にわたる質問〉としてみたところ、3回のインタビューの中で、「長い質問」がどの程度登場したのかを示したのが次の表である。
表6 40字で2行にわたる質問の出現回数
|
ほとんどは短い質問によって聞き取りが行われていたことがわかる。せいぜい20字前後の短い質問が中心である。
では質問の内容はどうか。質問の短さとつながるが、その内容も驚くほどシンプルである。まず第一に、〈人物・職業・地理の特定に関する質問〉がもっとも多い。
表7 中心となる質問項目
|
作品には記載されているのに、対象者に一度も質問されない事項がある。それは結婚や、入籍年、没年に関するもので、これらはすべて、調査者が戸籍を確認している。これは大変重要な点である。
表7からわかることは、調査の場面や状況、聞き方によって回答のバラツキのでない「事実」の特定に関する質問がすべてといっていい。これらの質問をどのように行うか。回答がなければ、質問の方向を変えたり、時間をずらして何度か同じ質問を繰り返す。つまり、簡潔な質問を短く、けれども念入りに行うのが中野の質問の特徴である。
アンケートに多用される意識調査の典型的な質問項目「〜についてどのようにお考えですか」という質問は、『口述の生活史』のインタビュー場面では一度しか登場しない。それは次のようなやりとりになっている。
表8 一度だけ登場した〈どのようにお考えですか〉という質問
|
一度だけ登場したこの質問は、よくみると、「はい」「いいえ」で答える質問の形になっているから、厳密に言えば、〈どのようにお考えですか〉質問より簡潔にされている。この部分が「公害の批判」として編集されている。(1977年版:276〜279ページ、1995年版:282〜285ページ)
以上をまとめると、『口述の生活史』における中野の聞き方は「いつ」「どこで」「だれが」といった短い質問によって構成されている点が特徴であり、「どのように思うか」「なぜか」という話者の回答が長くなるか、答えにくいか、それゆえに状況に依存して回答が変わる可能性のある質問は、ほとんど、あるいはまったく用いられない。
逆に言えば、聞き手の理論的関心、言いかえるとライフヒストリーによって明らかにしたいことが明確でなければ、以上のような特徴をもつ質問にはならないということである。こうした質問を経て、語りは話者の社会的世界として像を結び、作品化されていく。この質問が『口述の生活史』というライフヒストリーを「確かなもの」に構成している。
7. 作品化のプロセスからみた『口述の生活史』における「確かさ」
『口述の生活史』がライフヒストリー研究の分野で先駆的業績としてだけでなく、ライフヒストリー研究の中で一つのモデルを示しえているのはなぜか。その基本には、語り手への質問が明解であること、そして、話者の情動に対しコミュニケーション上、過度に親密な対応をせず、徹底して簡潔な質問を続け、話が展開すると、とことん、聞き手に回る。聞き方をつらぬくこの基本的姿勢が『口述の生活史』の「確かさ」を形成しているといえる。
1970年代後半から質的調査研究への関心が再び多様な方向性をもって展開されている中で、その一つであるライフヒストリー研究の分野ではライフヒストリーの名のもとに、さまざな成果が発表されている。ライフヒストリー研究がそうしたひろがりを見せる中で、モノグラフが「確かなもの」あるいは「安心して読める」14)ものとして信頼されるのは、どういう条件を備えた場合にそうなるのかを分節化してみたかったというのが、本稿を書く動機になっている。
『口述の生活史』の成立の舞台裏への関心が録音されたテープを聞きたいと思った最初の動機だったが、こうして「作品化のプロセス」を再び検討する作業を通じてわかったことは、話者の語りの作品化を支える中野の理論的関心の明解さであり、ライフヒストリーによって何を明らかにしたいのかという目的の明解さであった。
そうした聞き手を得て、70年以上も昔のことを、会話体で聞き手にリアリティをもってその当時の状況を再現できる語りの力をもつ話者の、語り手としての水準の高さ。『口述の生活史』は、この両者の出会いがつくりあげたモノグラフなのである。
《注》
1) 本稿は1999年1月9日関東社会学会研究例会(立教大学)において「質的調査研究における『信頼できる確かさ』の根拠」について報告する機会を与えられ、準備した原稿に加筆したものである。この研究例会のために報告者としてのご参加を快く承諾して下さった中野卓先生、および報告の機会を与えて下さった関東社会学会研究部会および司会の池岡義孝氏(早稲田大学)には記して感謝致します。
本文1)へ戻る
2) 中野卓「私の生涯における研究課題と方法」1994年12月21日最終講義(レジュメ)6ページ。
本文2)へ戻る
3) 「シリーズ座談 地域史構成のための視点をもとめて(19)」『歴史公論』1982年、10月号、129ページ。岩本由輝の氏発言など。
本文3)へ戻る
4) 水野節夫「生活史研究とその多様な展開」青井和夫監修/宮島 喬編集『社会学の歴史的展開』サイエンス社、1986年、184〜187ページ。
本文4)へ戻る
5) 大出春江「『口述の生活史』作品化のプロセス」中野卓・桜井厚編『ライフヒストリーの社会学』弘文堂、1995年。
本文5)へ戻る
6) 佐藤健二「ライフヒストリー研究の位相」中野卓・桜井厚編、前掲書、36ページ。
本文6)へ戻る
7) 小林多寿子「インタビューからライフヒストリーへ」中野卓・桜井厚編、前掲書。
本文7)へ戻る
8) 1999年1月9日関東社会学会研究例会での報告の後、席上で、中野卓氏からこの経緯について教えて頂いた。
本文8)へ戻る
9) 中野卓氏に伺ったところによると、呼松での調査でインタビューしたのは内海松代さんだけでなく、数名の人々にインタビューをしていたが、いずれも長い時間をかけて語る人生の語りが得られなかった、ということであった。1998年12月26日の聞き取りより。
本文9)へ戻る
10) 大出、前掲論文、95ページ。
本文10)へ戻る
11) 「この45〜6年、泣かされた」ことについて再度質問しなかったのはなぜかというわたしの質問に対し、中野卓氏は「『今はよくしてくれますぜ』という話者の先行した言葉の方が僕には響きましたから(「泣かされた」状況への質問は不要だ)」と答えている。1999年1月9日関東社会学会研究例会(立教大学)席上にて。
本文11)へ戻る
12) 大出、前掲論文、79〜80ページ。
本文12)へ戻る
13) 大出、前掲論文、97ページ。
本文13)へ戻る
14) 福岡安則「技法としての生活史聞き取り(2)」『解放社会学研究』10、1996年、79ページ。
本文14)へ戻る
 社会学研究室へ戻る
社会学研究室へ戻る